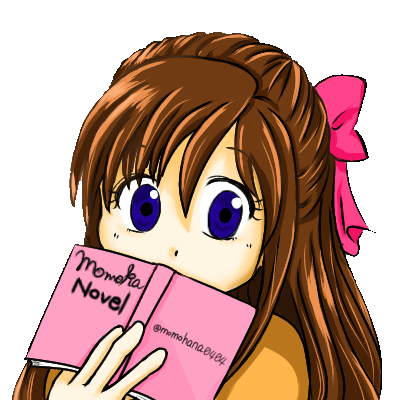
書くのが好きな桃花です。
今回は、HSPで電話が苦手な私が、
電話への抵抗感緩和のために、対策や思うことを綴ります。
HSPではないという方でも、電話が苦手という場合は、
一症例として参考にしていただきたいと思います。
私は医師でも専門家でもありませんので、こちらで記載している内容はあくまで個人的な体感と見解を述べているに過ぎません。一人一人によって原因や対処法なども異なりますので、鵜呑みにせずにあくまで参考としていただれば幸いです。
HSPと電話の相性
もちろんHSPにも様々なタイプの方がいらっしゃると思うので決めつけることは出来ないが、
電話が苦手というHSPの人は多いと思う。私なりに理由をあげてみると、次の通り。
- 何事をするにもじっくり考えてから行動するので、そもそも会話のキャッチボールが苦手(相手の言葉に返事をしたり反応したりするのに時間がかかりすぎる)。
- メール(文章)だと書き直しがきくが、電話(話)だと一度言ってしまうと修正がきかないと思い、返事を考え込んでしまう。
- 相手の様子が見えないので、雰囲気や細かいニュアンス(怒ってるのか冗談なのか等)を感じ取りにくく、どう返答していいかわからなくなってしまう(たくさん考えてしまう)。
- 常により良いものにブラッシュアップしていこうとする性質を持っているので、1つの返答が浮かんでも、「もっといい表現の仕方が無いか」と考えることを繰り返してしまい、言葉にならない。
- 着信音が鳴るとビックリしてしまう。
そもそも会話が苦手な上に、対面での会話ではカバー出来る〝雰囲気等からニュアンスを読み取る〟というメリットを差し引かれているために、さらに難易度が上がっている状況かと思う。
HSPの人は、時間をかけてでも相手により伝わるように、失礼のないように、確認を繰り返して自分が安心してから結果を相手に提供したい、という気持ちから、時間はかかるが文章(メール)で伝える方が楽、という方が多いのではないだろうか。
恐らく相性という点で、HSPには電話(会話)よりもメール(文章)の方が合っているのだろうと思う。もちろん、メールにしたからと言って楽チンになるかと言えばそう簡単なものでもなく、細かい、本当に些細なところまで何度もチェックして書き直したり、文章全体の流れを練り直したり、というのを繰り返すので、たかが1通のメールでさえ恐ろしいくらい時間はかかる。それで苦しんでいるHSPの人も少なくはないと思う。その点について取り上げる機会は今後に譲るとして、今回は、苦手な電話に対する抵抗感をどうにかして和らげられないか、ということについて、持論と、私なりの対処法について述べる。
電話の際に生じる反応
元々、電話は得意では無かったが、仕事で電話は必須事項だから、苦手なりによく使うツールとして利用していた。
私は公務員をしていて、関係者の方々に手続きのお願いをする、という仕事をしている。当然の反応であるとも言えるが、協力を拒否する方や怒り出す方、不信感をぶつけてくる方も少なくない。
以前、協力をお願いしたい何十名の方々に電話で説明をするということを行った。他の職員であれば頭の中の情報だけで説明出来る人がほとんどだが、私はうまく話せる自信が無かったので、説明のためにカンペを作った。想定される質問とそれへの返答をいろんなバージョンで考え、印刷してそれを見ながら電話をかけた。幸いなことに、優しく話を聞いて下さる方もいらっしゃったが、案の定反発される方もいた。
ある方と電話した時に、怒りをぶつけられ、その瞬間、頭が真っ白になった。何を言われても言葉が出ず、ただ相手の怒りが電話口から流れてくるのを、黙って聞いていることしか出来なかった。どのくらいそうしていたのだろうか。10分とか15分だったのかもしれないが、世界が一気に凍結してしまったみたいだった。ただただ怖くて、固まっていた。
あの時の状況を言葉で説明しようとすると、脳が危険のアラームを鳴らし、恐怖が胸を占め尽くし、考えることや反応することを遮断することで、メンタルが崩壊しようとするのを回避しようとしているみたいだった。つまり、極度のストレスからの防衛反応だった訳だ。
何が起きているのか
- 頭が真っ白になる。
- パニックになる。
- フリーズする。
- 言葉が出てこない。
これらはいずれも同じ状況を現した表現だが、脳になんらかの反応が起きていると考えてよさそうだ。
人はストレスに晒されると、身を守るために何かしらの反応をするが、代表的なものとして、脳にある扁桃体の反応があげられる。扁桃体は身の安全に関わる情報を瞬時に判断し、命に関わる不快・危険な刺激だと感じると、「闘え」か「逃げろ」という指令を出す。そして、それさえも妨げられた状態になると、〝凍りつく防衛スタイル〟になるのだそうだ(参考サイト:トラウマケア専門 こころのえ相談室)。
また、「頭が真っ白になる」というのを、〝プチ解離〟と表現しているサイトがあった(参考サイト:インナーチャイルドケア講座)。私としてはこの説明がしっくりきたので引用させていただきながら言及すると、確かに子どもの頃の記憶を遡ると、母親の怒った顔しか思い出すことが出来ない。あの頃はトラウマになるほどの記憶という認識では無かったが、今でも電話に限らず、怒鳴る人や声を荒げる人を前にすると、脳が消灯するようにプツリと機能オフになってしまってフリーズしてしまう。恐怖が行き過ぎて対処不能になった状態だ。
つまり、身の危険を感じる程のストレス(あるいは引き金となる刺激)に直面すると、脳が指令を出し、思考も全身もフリーズ状態になってしまう。動物で言うところの〝死んだふり状態〟に陥るのだ。
※専門的に「トラウマ」とは戦争などの強烈体験からくるものを指すそうだが、本記事内ではもっと広範囲の言葉として用いることとする。
「闘う」のがいいのか、「逃げる」のがいいのか
苦手な電話から、「闘う」のがいいのか、「逃げる」のがいいのか。
これに関して、よく耳にするHSP向けの対策理論からいくと、
「苦手なことはいくらやってもダメ、できるだけ避けた方がいい」(=逃げろ)ということが言われそうだ。
確かに、本当にダメなものはやっぱりダメなので、昭和平成的な根性論で
「弱音なんて吐いてられるかあうおおおお!!」
と立ち向かっても、闇雲にやればメンタル病んでしまうことだってあるだろう。
もしも、他の人に頼む、等で避けられそうな場合は、避けるのも手だ。
だが、仕事における電話はかなり必須度の高いタスク項目なので、実際逃げられない、ということの方が多いのではないだろうか。
さらに、〝逃げる〟ことは一時的な回避策にしかならず、一生逃げ続けなければなくなる。
私が最も危惧するのは、避げれば避げる程どんどん電話抵抗感が強まり、次にその機会に遭遇した際、弱体化した状況で対峙しなければならなくなる、ということだ。
もちろん、無理はいけない。ひどい時はどう頑張っても無理だ。だが、少しでも出来る範囲を広げていければ、心に余裕が出来る。出来れば皆さんには、電話が〝得意〟とまではいかなくとも、最低限通話くらいなら出来る、くらいまでには抵抗感を緩めていただきたいと思う(自分も含め)。
思うに、HSPの人で電話が苦手な人は少なくないだろうが、慣れればある程度、もしくは話し上手の人以上に電話が上手くなる可能性は大いにあると思っている。
「逃げる」方がいい場合
「なるべく電話から逃げないで少しずつ慣れた方がいい」と言ったものの、調べた内容や体感から、思ったことがある。
HSP=電話が苦手な人が比較的多い(推測)
が、
頭が真っ白になるのは、メンタル(トラウマ等)関係に原因がある可能性が高い
ということだ。
「頭が真っ白になる」「フリーズする」といった状況は、もはや克服可能な〝苦手〟という領域からは逸脱してしまっている(体感)。また、脳が強烈に〝拒絶〟という方法を選択する、脳の軽い異常状態ではないかと感じている(体感)。
私も上記の状況になった後も電話をかけ続けたが、結局そのままメンタル的にその他の部分も含めてダメになってしまった。そのため、電話など特定の状況下で「頭が真っ白になる」という症状をお持ちの方は、メンタル関係の原因を探ってみることを優先していただきたい。
その上で、原因に目処がつき、症状が落ち着いてきた方は、以下を参考に、少しずつ電話への抵抗感を和らげていっていただければ嬉しく思う。
また、
電話をかけることは〝苦手〟ではあるが極度の恐怖感までは感じない方
電話対応が〝苦手〟だけどもっと上達させたい方
についても、主にHSP目線から電話の苦手克服法について思うところを述べていくので、参考にしていただきたい。
電話対応~マインド編~
具体的な方法の前に、頭に入れておくだけで少し心の緊張をほぐせるような考え方をいくつかピックアップしてみる。どれも基本的なマインドだが、電話に限らず、仕事の他の面でも通用する考え方だ。
場数(練習)が必要
仕事における電話対応がどういうものか覚えるにあたり、最初からうまく出来る人などほとんどいない。やはり、単純に数をこなせばそれだけ慣れるし、スムーズに話せるようになっていくものだ。電話も、いくつかの決まったパターンの組み合わせによるものが大部分を占める。そのパターンを知ること、人によって異なる話し方の個性を知ること、などで、着実に通話は上達していくと言える。
失敗から学び、ブラッシュアップすることで成長する
特に最初は、うまく話せないことや取り次いだ上司からの指摘などで、自己嫌悪することもあるだろう。特にHSPなら、一見些細な出来事でもずっと引きずって落ち込んでしまうことも多い。
だが、失敗したということは、1つ改善出来る点がわかった、ということである。相手方の連絡先を聞きそびれて叱られたのであれば、「○○の時には相手方の連絡先を聞くとよい」という知識を1つ覚えたということ。次は反省を生かしてよりレベルアップした電話スキルで応対しよう。また、相手とのやりとりで落ち込むこともあるかもしれない。その時も、何をどうすれば良かったのか、という点を振り返り、次回はそのように対応してみよう。
そのそうやって少しずつ電話スキルなるものを増やしていくのだ。最初は失敗だらけで辛いと感じるかもしれないが、スキルを習得していくゲーム感覚でやると、さほど緊張せず楽しく覚えていけるに違いない。
注意すべき点は、うまく通話出来なかった自分を責めない、ということだ。自分責めが良くない、ということはもちろんだが、これがクセになってしまうと、電話のたびに「また次もうまく話せないかもしれない」と言う恐怖を感じるようになり、それが負のループを生んでしまう。失敗から学べる点を拾い上げたら、あとは忘れるくらいでちょうどいいのだ。
失敗しても、命を取られるわけではない
どんなに電話で心理的に怖い思いや恥ずかしい思いをしたところで、すぐさま命を取られる訳ではない。私も机の上に、「電話は噛み付かない」と書いたメモを置いている。
まぁ、頭でわかっていても怖いものは怖いし、一度真っ白になってしまうとそんなこと頭から吹っ飛んでしまうのではあるが……。
それでも、どんなに相手が怒鳴ってきても罵ってきても、可能な限りの冷静さを保てるかどうかは、
- 今相手は感情的になっているのだな、ふむふむ。【客観的に分析する視点】
- 相手は私個人を攻撃しているのではなく、会社全体を罵倒しているのだ。【担当窓口としてのみ話を聞いている立場である自覚】
- 別にこの人と個人的に仲良くする必要はなく、あくまで一職員として話をしているだけ。【オフィシャルなだけの関係性である認識】
という考え方がしっかりベースにあるかどうかにかかっていると思う。
HSPは、声色だとかイントネーションとかの細かい部分で相手の感情までをも感じ取ってしまい、それに埋もれてしまうため、一度感情をぶつけられると冷静でいられなくなってしまいがちだ。
でも、少しでも上記のことを頭に入れておいて、半ば機械のように対応をしていくことも必要だろう。
完璧に話そうとしない
電話となると、「この1回の電話の中で完璧な返答をしなければ」と思っていないだろうか。
もちろん、それが出来ればベストなのだが、一度の電話で解決できない話や、話が前進しないで終わってしまう電話もあるし、話し手側として失敗だらけの通話だったりすることなんてよくあることだ。
スムーズに話すことが苦手なHSPの人は、よどみなく喋る人に憧れることも多いだろう。だが、話が上手いと感じるその人も、「うーん」とか「ええと」などで考える時間は取っているものだ。
HSPは、電話が終わってからも「あの人はああ言いたかったんだろうか」「自分の聞き方が悪かっただろうか」などとしばらく考え込んでしまうものだが、〝完璧じゃなくていい〝。この言葉を心の中で呟いて、ぐるぐる反省会をするのは程々にして欲しい。終わってしまった電話は終わってしまったのだ。もし足りないと思う点があれば、相手からまた電話が来るだろう。それでいいのだ。
それと、「完璧に話さないと」と思うあまり、言葉に詰まってしまうことが往々にしてある。考えれば考える程頭がいっぱいになってしまい、なんて説明すればいいかもわからなくなってしまうのだ。そんな方には、いったん電話を切る、という方法をオススメする。
「内容を確認させていただき、後ほど改めてお電話差し上げてもよろしいでしょうか?」
などと言って、一度電話から離れるのだ。
説明する側の頭がいっぱいになっている状態で、無理に電話を続けても何も進展しない。しどろもどろに説明したり間違った情報を伝えたりするよりは、一度落ち着く時間を設けた方がいい。特にHSPはこの状況に陥ることが多いと思うので、ぜひ覚えておいて欲しい。中断させるのは悪いことではない。これも電話スキルの1つなのだ。
電話対応~対処法編~
さて、ここからは具体的な対策法についてあげていく。
マイマニュアルを準備する
HSPは、より伝わるように言うにはどう言ったらいいか、と考え込んで、「もっといい言い方は……」を頭の中でループしてしまうので、沈黙が長くなってしまうのだ。
そのため、こう言われたらこう返答する、という言い回しをストックしておこう。
返答をパターン化することで、あれこれ考えずに返答することが出来、沈黙の時間を減らして脳のエネルギー消費も少なくすることが可能だ。また、事前に紙に印刷しておくことで、頭が真っ白になった時用のお守りとして心強い役割を果たしてくれる。
事前に準備しておくものとして特にオススメなのは、先の項目「完璧に話そうとしない」でも紹介した、いったん返答を保留にするための言い回しだ。
- このままお待ちいただいてもよろしいでしょうか?
[他の人に代わってもらう時、少し落ち着きたい時、等 多用可能] - ただいま確認いたしますので、少々お時間いただいてもよろしいでしょうか?
[脳がいっぱいになって落ち着きたい時の保留休憩用にも利用可] - 確認して、後ほど(後日)ご返答差し上げてもよろしいでしょうか?
- お話する内容を再度まとめて、改めてお電話差し上げてもよろしいでしょうか?
[説明が自分でもとりとめなくなってきたと感じた時等]
準備すべきマイマニュアルの中でも、特にHSP視点で注意しておいた方がいいと考えるのは、
敬語だ。
HSPは、相手に失礼で無いか、ということを物凄く気にする。そのため、1つの返答が頭に浮かんでも、それをその言葉で言って相手の気分を害することはないだろうか、と考え込んでしまい、つい言葉に詰まってしまうということがよくある。
そこで引っかかってくるのが敬語だ。これで正しいのだろうか、尊敬語と謙譲語が逆ではないか、咄嗟のことで表現が思い出せなくなってしまった、といったことがよくある。電話は、なぜかストップウォッチを押されたような緊張感があるのでついつい焦ってしまうが、これも基本的な言い回しを準備しておき、少しずつストックを増やしていこう。代表的な敬語をあげてみる。
- ただいま代わります(おつなぎします)のでお待ちください。
- ○○は、本日不在にしております。
[・対外的には、内部の人間は上司であろうと呼び捨て(名字のみ等)で言う。
・「出かけております」「お休みしております」等まとめて通じる「不在」がベスト。] - かしこまりました。伝えておきます。
[伝えてください、と伝言を言われて。] - 念のため、ご連絡先をお伺いしてもよろしいでしょうか?……復誦いたします。……
上記は本当に基本的なものなので、他の状況も調べたりしながら、自分が言いやすく口馴染みのいい言葉を選んでいこう。より敬語のレベルや配慮度合いを上げていくと実践で役立つ。
ポイントとして、最初は出来るだけあらゆるパターンの際に応用のきくものを少数準備しておくのがいい。バリエーションが多すぎると脳が混乱するので、返答パターンは出来るだけ絞り、余力が出てきたら増やしていくのがいいだろう。
マニュアル準備の際は、実際に会話をしている時を想定しながら自分の話す内容を書き出してみるといい。そうすることでいろんなバージョンに対してスムーズに対応することが出来る上、シミュレーションで練習にもなる。
うまい人をまねる・参考にする
他の人がどのように話をしているのか、注意深く聞いてみよう。そして参考になるポイントがあったら、出来るだけメモしておこう。記憶だけで覚えておこうとしても、実際に自分の番になると頭から飛んでしまうことがほとんどだ。メモしておくと、意識するポイントが明確になるので記憶に残りやすく、かつ、通話中に目を通すことでさらに自分のスキルとして定着させやすくなる。
さらには、電話で心がけているポイントも人によって異なる。ある同僚がほぼ毎回確認している点を覚えておくことで、その人宛の電話を不在時に取った場合、確認しておく点の予想がつけられるかもしれない。(例:連絡可能時間帯を聞く、名前をフルネームで聞く、処理ナンバー等を聞く、など。)
自分のクセを発見する・指摘してもらう
自分の電話対応を客観的に知るという意味で、他の人から教えてもらう、ということもよいことだ。こうすることで、〝他の人が気になる点をピンポイントで練習・改善していける〟ばかりでなく、
〝自分は苦手だと思っていたポイントも、他の人から見たら欠点という程でも無い〟
ということに気づくことがある。
たとえば、相手への返答に対して時間ががかりすぎていることをコンプレックスに感じているとしよう。だが、実際はそんなに相手を待たせている訳では無い、ということもあったりする。沈黙に対する抵抗が強すぎて、自分ばかりが妙に意識しすぎてしまうのだ。そしてそれは、思い込みによることが多いので、自分では気づきにくい。自分で苦手だと感じている項目について、「私の電話対応の○○は適切でしょうか?」と具体的に聞いてみるのもいいだろう。目からウロコ的に、苦手そのものがかき消えるかもしれない。
職場の人には聞きにくい、という場合は、出来れば気心の知れた知人などにも聞いてみて欲しいと思う。職場の話し方とは別物かもしれないが、普段の話し方の間合いなどと比較することくらいは出来るだろう。
きっかけ(トリガー=引き金)となるポイントを探す
脳は情報を関連づけて整理することが得意なので、思考や身体の反応の多くは、向けられた情報の持つ何らかの刺激を元に推測された結果だ。一度電話が苦手になると、電話の音を聞くだけで反射的に体が強張るということが起きる。この場合、電話の音がトリガー(=引き金)だ。
特に、感情に強く残っている記憶や繰り返し刻み込まれた記憶は、無意識にも脳が強く記憶を引っ張り出してしまう。そしてその関連性は、必ずしも直接的に関連性の無いものである場合もある。たとえば、蜂に刺された人が森のにおいを嫌がったりするなどだ。脳は危険を回避するため、関連性のあると考えられるものを無自覚にもつなげてしまう場合がある。
もしその原因と反応との関連性を曖昧にしてしまうと、本来であれば避けられるはずの苦しみも広範囲まで広げていってしまう可能性が出てきてしまう。「電話で話すのが苦手→電話が鳴るだけでドキドキする→電話が怖くて職場に行くのが億劫」と、どんどん恐怖の対象が広がっていってしまうことになりかねない。
そのため、
- 電話の中でも何が苦手なのか。
- 相手次第なら、どういう相手からの電話が苦手なのか。
- どういう内容の話題が苦手なのか。
ということなどを自分の中で整理して、きっかけ(トリガー)や原因を出来るだけ限定しておいた方がいい。
また、フリーズしてしまう原因を知ることで、ピンポイントに絞った対策が出来るかもしれない。具体的には、商品の説明が苦手なのか、トークスキルなのか、怒鳴る人だけ苦手なのか、などだ。特定の話題になったら、別の人に変わってもらうなど工夫出来る場合もあるかもしれない。電話そのものが苦手なのではなく、特定の条件(相手が年上の女性の場合、相手の黙っている時間が長すぎる場合、相手が早口の場合、など)がトリガーになっている場合は、そのことが過去のトラウマと関わっている場合も少なくない。
私の場合は、「電話で怒鳴られた」という経験が自分の中で大きく膨らんでしまい、脳が〝電話〟と〝恐怖〟を結びつけてしまった。そもそも話すことが苦手な部分もあったが、恐怖に関わる脳の関連付け瞬発力は物凄い。原因を分解していくことで、恐怖の対象を小さくしていくことが出来る。
まとめ
大前提として、
- 電話が苦手でも、出来る限り逃げずに練習して、少しでも抵抗感を弱めるようにする方がいい。
- ただし無理はしないこと。毎回頭が真っ白になる場合は、トラウマなどメンタル面での原因がある場合が考えられるので、そちらからアプローチしてみることも検討する。
その上で、電話の苦手克服のための心得と対策は次の通り。
- 数をこなすことで上達する。
- 失敗から学びを得て改善につなげる。
- 完璧に話そうとしない。
- 相手の感情に飲み込まれず、客観的に分析する視点を持つ。
- 職場という組織の中の1担当者として話している冷静な意識を持つ。
- マイマニュアルを準備する。(広く使えるものを少数)
- 敬語を抑えておくとより安心出来る。
- 頭が混乱してきたら一度話を中断することを考える。
- 「電話=苦手」と思い込まず、苦手な範囲を絞る。
苦手なことに向き合うのはしんどいことだが、無理の無い範囲で少しずつ〝苦手〟を緩めていっていただければ幸いだ。
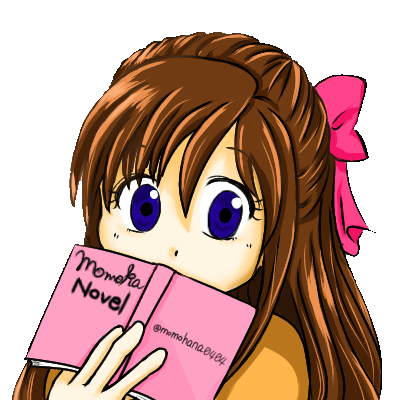
今も電話の苦手感はやはり克服出来ません。
トラウマ解消未了なので、トリガー(怒鳴られる)が起きると今も恐怖に縛られて頭が真っ白になります。少しずつトラウマを癒していきたいと思います。

.png)
-120x68.png)
-120x68.png)
コメント